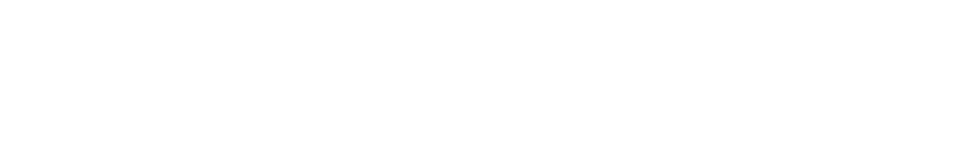お知らせ
NEWS
矯正で医療費控除は受けられる?いくら戻るかや条件も解説

歯並びをきれいにしたいけど、費用が気になる方も多いのではないでしょうか。高額になりがちな矯正治療費は、条件に当てはまっていれば、医療費控除の対象になる場合があります。
この記事では、矯正治療で医療費控除が受けられるのか、いくら戻ってくるのか、どのような条件が必要なのかをわかりやすく解説します。
矯正治療を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも医療費控除とは?

医療費控除は、簡単に言えば一定の医療費がかかった場合に所得税が減額される制度のことです。1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合に確定申告を行うことで、超過分が所得から控除され、所得税が軽減されます。
必要な書類を揃えれば、確定申告はそれほど難しい手続きではありません。
医療費控除の対象となる医療費は、以下の通りです。
| 病院や診療所で支払った医療費 |
|
|---|---|
| 歯科医院で支払った医療費 |
|
| 特定の医療機器の購入費 |
|
| 介護保険で支払った費用 |
|
矯正をした際の医療費控除の対象となる費用

一般的に、矯正をした際の医療費は、以下が控除の対象になります。
治療に必要な費用
- 検査料
- 診断料
- 処置料
- 抜歯費用
- 装置費用
- 調整料
通院費
- 通院のために公共交通機関を利用した場合の交通費
医療費控除の申告の際には、どのくらいの費用がかかったのかの証明のために領収書・明細書・通院日時が記載された診察券などが必要なので、大切に保管しておきましょう。
領収書が発行できないバスや電車の公共交通機関の費用は、利用日時や費用は都度記録しておくと申告がスムーズです。
矯正治療を受けるのが小さな子供で通院に付き添いが必要な場合は、付き添う人の交通費も通院費に含まれます。
参考:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
矯正をした際の医療費控除の対象とならない費用

矯正治療が医療費控除の対象になるといっても、医療費控除は全ての費用で対象になるわけではありません。以下の費用は、矯正医療費控除の対象外です。
- 歯並びを美しくしたいという美容目的のみの治療費
- 治療に必須ではない病気の予防や健康増進など予防目的の治療費
- 治療に必要な範囲を超えた、高額な材料を使った治療費
- デンタルローンやクレジットカードの分割払いの金利や手数料
- 通院に自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代
- 診断書の発行にかかる費用
バスや電車などの公共交通機関の通院費は矯正医療費控除の対象ですが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外なので注意が必要です。
デンタルローンやクレジットカードで治療費を分割払いした場合でも、美容目的でなければ治療費は矯正医療費控除の対象となります。
分割払いで支払いを行って手元に領収書がない場合、デンタルローン契約書や信販会社の領収書が証明書として活用できるので、大切に保管するようにしてください。
参考:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
矯正の医療費が控除の対象になる条件

矯正治療の費用は、全てが医療費控除の対象になるわけではありません。控除を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 美容目的ではなく、機能的な問題を改善する治療
- 成長期の子供の治療
- 家族の年間医療費が原則10万円以上
それぞれの条件を詳しくチェックしてみましょう。
機能的な問題を改善する治療の場合
噛み合わせの改善や発音の改善など、機能的な問題を解決するための治療は、矯正医療費控除の対象です。単に歯並びを良くしたいという美容目的は、矯正医療費控除の対象外となります。
矯正医療費控除の対象となる機能的な問題は、
- 歯並びが悪く、ご飯が食べにくい
- 顎関節症のようなあごの病気の治療を受けている
- 出っ歯や受け口で発音がうまくできない
- 歯並びが悪く、歯周病になりやすい
などが挙げられます。
成長期の子供が矯正する場合
成長期の子供が矯正治療は、
- 顎の発育を誘導する
- 永久歯が生えるスペースを確保する
などの理由で矯正治療を受けることがほとんどでしょう。
発育途中の子供の成長を妨げないようにするための矯正治療は、矯正医療費控除の対象となります。大人の矯正治療は、機能的な問題を改善する場合のみ対象です。
成長期の子供が矯正するのは、
- 成長期は骨の柔軟性が高く矯正治療の効果が得られやすい
- 大人に比べて短い治療期間で矯正が終了する
- 抜歯の可能性を抑えられる
- 顔のバランスが改善される
- 虫歯や歯周病のリスクが減り、生涯健康な歯を保てる
などのメリットも挙げられます。
家族の年間医療費が原則10万円以上の場合
家族の年間医療費が原則10万円以上というのは医療費控除を受けるための一般的な条件であり、矯正治療に限ったものではありません。
家族全員の医療費の年間合計が10万円を超えた場合、超過分は所得税から控除を受けられます。
医療費控除の計算方法

医療費控除の計算方法は、所得額によって若干異なります。
医療費控除額の計算
(A)年間医療費の合計額-(B)保険金などの補てん金額-(C)10万円または総所得の5%
(A)年間医療費の合計額
矯正治療にかかった費用だけでなく、その他の医療費も全て合算します。
(B)保険金などの補てん金額
医療保険などから支払われた金額は、控除の対象から除きます。
(C)10万円または総所得の5%:
総所得が200万円以上の場合: 10万円を差し引きます。
総所得が200万円未満の場合: 総所得額に5%をかけた分を差し引きます。
計算例
| 家族 | 総所得(万円) | 年間医療費(万円) | 保険金(万円) | 医療費控除額(万円) |
| A | 450 | 75 | 15 | 50 |
| B | 180 | 30 | 8 | 13 |
Aの場合:高所得世帯で、矯正治療費以外にも医療費がかかったケース
医療費控除額=75万円-15万円-10万円=50万円
Bの場合:低所得世帯で、矯正治療費が主な医療費のケース
医療費控除額=30万円-8万円-(180万円×5%)=13万円
続いて、どれだけお金が戻ってくるのかの還付金の計算を行います。
還付金は医療費控除額に、所得税率をかけます。所得税率は、所得金額によって異なります。
令和6年分の所得税の税率は以下の通りです。
| 所得合計金額(課税所得額) | 税率 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,0000円以上 | 45% |
Aの場合:総所得450万円で税率は20%
還付金 = 50万円×20%=10万円
Bの場合:総所得180万円で税率は5%
還付金=13万円×5%= 6,500円
確定申告で医療費控除を申請すると、翌年の住民税も減税されます。減額されるのは、医療費控除額の10%です。
Aの場合:50万円×10%=5万円
Bの場合:13万円×10%=1万3,000円
所得税率は課税所得に応じて適用されますが、課税所得は総所得から各種控除を差し引いた金額です。今回の計算では総所得をそのまま使用していますが、厳密には課税所得を算出する必要があります。
還付金額や住民税の減額額は、他の控除や税額控除の適用状況によっても変動する可能性があります。正確な金額を算出するためには、税理士や税務署への相談がおすすめです。
上記の計算例はあくまで目安として参考にしてみてください。
矯正医療費控除の手続きのやり方や必要な書類

矯正医療費控除の手続きは、以下の流れで進めていきます。
確定申告の準備
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に行われます。前年分の所得に対して申告を行うので、早めに準備を始めましょう。
必要書類の準備
以下の書類を揃えます。
矯正医療費控除に必要な書類の詳細
| 書類名 | 内容・ポイント |
| 確定申告書 | 収入や所得、控除項目を記入する基本書類。 |
| 国税庁のサイトからダウンロードまたは税務署で入手可能。 | |
| 医療費の明細書 | 支払った医療費の詳細を記入する書類。 |
| 医療機関名、治療内容、金額などを明記。 | |
| 領収書 | 実際に支払った費用を証明する書類。 |
| 原本の提出、必要に応じてコピーを添付。 | |
| 治療証明書類 | 医師が発行する診断書や矯正治療の必要性を示す書類。 |
| 医療上の必要性を証明。 | |
| 保険金等の受取証明書 | 医療費の一部が保険等で補填された場合の金額を証明する書類。 |
費用の集計
矯正治療にかかった総費用を集計します。保険等で補填された金額を差し引いた後の額が控除対象です。
医療費明細書の作成
支払った医療費の日付・支払先・項目・金額などを詳細に記入します。
確定申告書への記入
確定申告書に必要事項を記入し、医療費控除の欄に該当する金額を入力します。
書類の提出
すべての書類を揃え、税務署に提出します。電子申告(e-Tax)を利用する場合は、オンラインでの提出が可能です。
控除の適用
申告内容が確認されると、所得税が減額されます。還付金が発生する場合は、指定した銀行口座に振り込まれます。
確定申告は毎年決まった期間内に行う必要があります。期限を過ぎると控除を受けられなくなるため、早めの準備を心がけましょう。
不明点や複雑なケースは、税務署や税理士に相談して正確に申告しましょう。
矯正をした際の医療費控除に関するよくある質問

矯正をした際、医療費控除に関するよくある質問をまとめています。疑問点を解決して、矯正医療費控除の申請に臨みましょう。
矯正の医療費控除に診断書はいらない?なしでも大丈夫?
診断書は、医療費控除を申請するために必要です。
医療費控除を受けるためには、治療が「医学的に必要」と証明しなければなりません。治療の必要性を示すために、診断書の提出が求められます。
診断書がない場合でも、矯正治療計画書や医療機関からの証明書で治療が医学的に必要と証明できる場合があります。確実に控除を受けるために、診断書を準備しておくのがおすすめです。
矯正の医療費控除申請に期限はある?
矯正を含む医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があり、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
確定申告の期限を過ぎて申告すると、控除を受けられなくなります。ただし、還付申告(払いすぎた所得税の還付を求める申告)として、申告期限後でも5年間は申告が可能です。
矯正用歯ブラシや洗浄剤は医療費控除の対象になる?
矯正用の特殊な歯ブラシや洗浄剤は、通常の口腔衛生を維持するための一般的な製品として扱われるケースが多く、医療費控除の対象になりません。
ただし、医師または歯科医師の処方や指示がある・治療に直接関連しているなどの条件を満たしている場合、医療費控除の対象となる可能性があります。医師や歯科医師からの指示書や処方箋に購入理由を明記してもらうと、税務署に対する証明がスムーズです。
医療費控除の申請はどこからすればいい?
申請は、
- 居住地を管轄する税務署の窓口に直接提出
- 居住地を管轄する税務署に郵送して提出
- e-Tax(電子申告)の利用
で行えます。
医療費控除を活用して、矯正治療をお得に始めよう

矯正治療は高額な治療費がかかってしまうのが現実です。しかし、医療費控除制度を活用すると、経済的な負担を軽減して矯正治療が受けられます。矯正治療を検討している方は、医療費控除の対象なのか、どのくらいのお金が戻ってくるのかをチェックしてみてください。